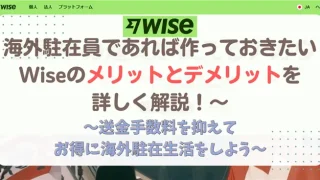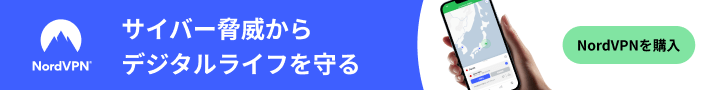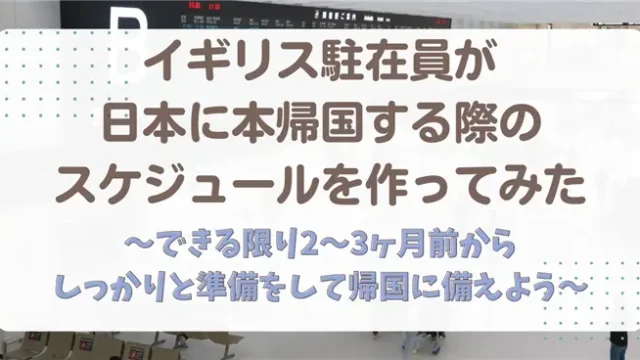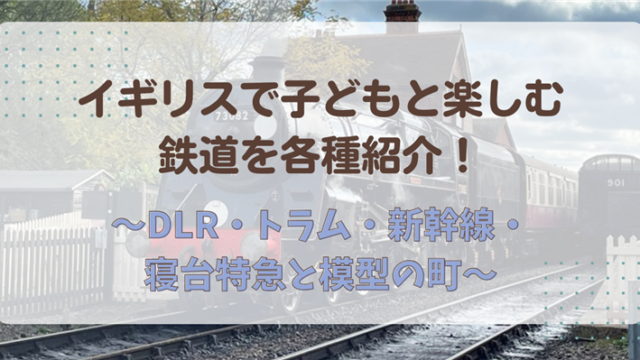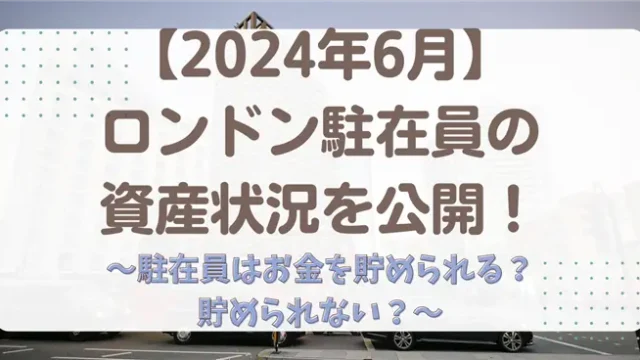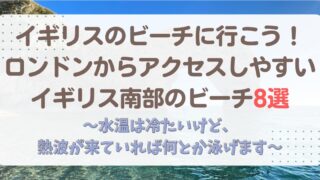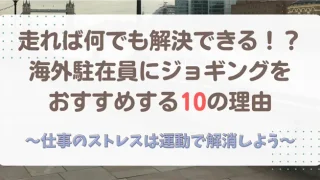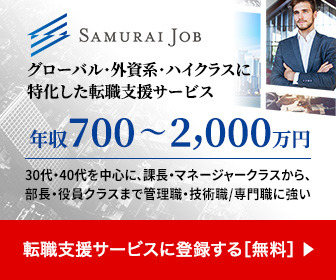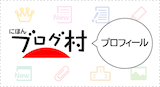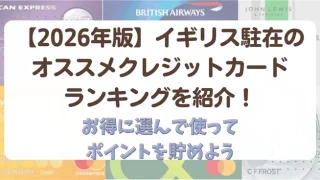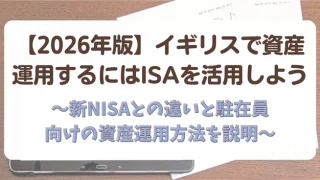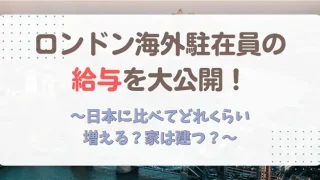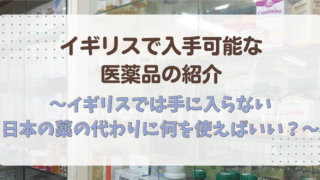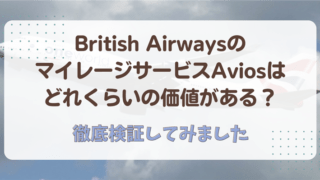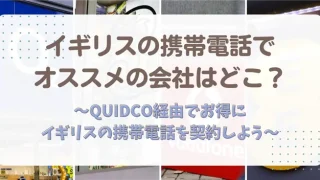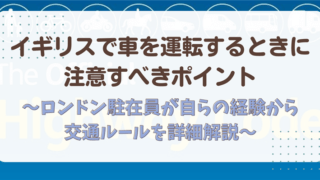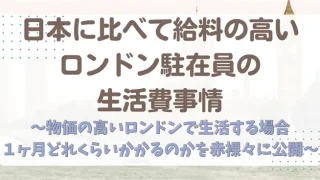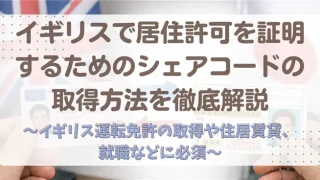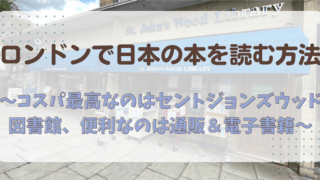海外駐在員は本当に大変!メンタルを病まないようにするための心構えと対策~海外で働いているあなたはそれだけですごい~
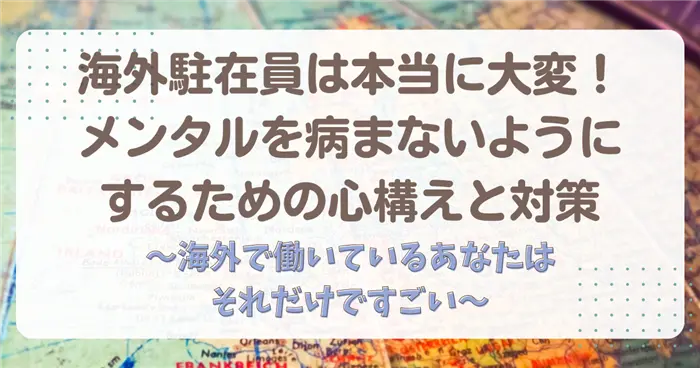
どうも、ロンドン駐在員のぷーたです。
今回の記事は、次のような方の疑問を解決するために書いています。
- 海外駐在員は楽してお金をもらえるように見えるけど、仕事は大変なの?
- 海外駐在員が気をつけなければいけないことは?
- 海外駐在員がメンタルを壊してしまうことが多いって本当?
<広告>
筆者のぷーたはイギリス駐在員を始めとする海外で生活する方にWiseのアカウントを作成することをおすすめしています。
Wiseのアカウント登録は、下にあるボタンから簡単にできます。日本にいる時からWiseアカウントは作成できますので、いざという時の安心のために、海外へ行く前に作っておくことをおすすめしますが、すでに海外に到着していても、住所が定まっていればイギリスをはじめ多くの国でアカウント登録が可能です。
こちらのボタンからWiseに登録すると、通常発行手数料が1,200円かかるWiseデビットカード、または最大75,000円までの送金に使えるクーポンのどちらかが無料でもらえます。
↓Wiseのアカウント登録(無料)はこちらから↓
Wiseの詳細情報、利用するメリット・デメリット、海外駐在員の利用するシーンなどはこちらの記事でくわしく解説していますので、よろしければご覧ください。
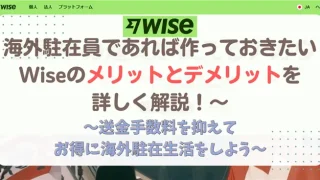
海外駐在員のメンタルは大変
 最初に言っておきますが、海外駐在員は大変です。これはあまり一般には知られていないかもしれませんが、断言できます。そして、残念ながらせっかく海外駐在員として海外に赴任しながらも、メンタルのトラブルを抱えて帰国せざるを得なくなってしまう方も多いです。
最初に言っておきますが、海外駐在員は大変です。これはあまり一般には知られていないかもしれませんが、断言できます。そして、残念ながらせっかく海外駐在員として海外に赴任しながらも、メンタルのトラブルを抱えて帰国せざるを得なくなってしまう方も多いです。
ですが、私が感じているのは表面的には出ていないものの、内側でメンタルの問題を抱えている駐在員の方が信じられないくらい多いです。表面に出てこないため、外から見てもわからないことが多いのですが、私は友人に過去メンタルの問題を抱えて会社を休んだ方が何人もおり、そういった友人に話を聞くと、みんな揃って「自分がメンタルの問題を抱えてみて初めて、同じようにメンタルの問題がある人が多いことを知った」と言っています。
つまり、メンタルヘルスの問題が表面化して初めて他人に悩みを共有して、実は相手も問題を抱えていたことがわかる、というパターンが多いんですね。海外駐在員の場合、海外駐在員になる経緯や環境の変化、家族との関係などメンタルにマイナスの影響を与えることが日本国内勤務に比べて非常に多いため、ただ海外で生活して働いているだけで、信じられないくらいすごいということを言いたいと思います。

海外駐在員の抱えるストレスは膨大
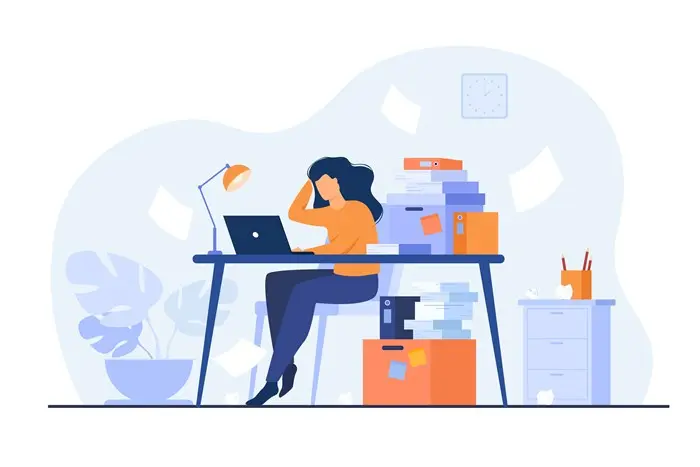 私は現在ロンドンで海外駐在員をしています。グローバル化が進んで、大企業に勤務しているのであれば海外駐在をすることはそう珍しいことではなくなっています。そして海外駐在する方は、基本的には日本で業績を上げていて、海外で仕事をしても問題ないタフさやレジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を有している、いわばエリートの方だと思います。
私は現在ロンドンで海外駐在員をしています。グローバル化が進んで、大企業に勤務しているのであれば海外駐在をすることはそう珍しいことではなくなっています。そして海外駐在する方は、基本的には日本で業績を上げていて、海外で仕事をしても問題ないタフさやレジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を有している、いわばエリートの方だと思います。
ですが、一方で慣れない生活環境、言語の壁、孤独感、家族の適応など、多くのストレスを伴うことも事実です。私の場合、言語は英語、世界でも有数の先進国であるイギリスにいるわけですから、他の非英語圏や発展途上国に赴任するよりもずっと楽なはずですが、実際はものすごく大変です。
感覚としては、イギリスにいると、ゲームで言う最大HP(体力)が半分くらいになってしまう感覚です。最大HPなので、いくら寝たりリラックスしたりといった回復手段を用いても、半分までしか体力が回復しません。実際の体力で言えば、私の場合フルマラソンをそれなりのスピードで完走できるくらいの体力はあるのですが、全体的な能力というか、できることが半分くらいになっているイメージです。
誇張もあると思われるかもしれませんが、生活のありとあらゆるところでギャップを感じるのは事実ですし、あらゆるルールや物事を確認するにも、言語というよりはそもそもの文化や価値観が異なることから戸惑うことが多いです。そのため、海外駐在を始める際には思ったような生活はできないと思うことから始めなければなりませんし、仕事に関してはそれ以上にうまく行きません。


海外駐在員の表からは見えないストレス
 私も海外駐在をしている立場のため、ストレスを感じることは非常に多いです。私が考える海外駐在員のストレスについて、5つの要因に分けてみました。
私も海外駐在をしている立場のため、ストレスを感じることは非常に多いです。私が考える海外駐在員のストレスについて、5つの要因に分けてみました。
- 文化・価値観の違い
- 仕事の成果に対するプレッシャー
- プライベートの問題(家族に関する問題/単身での孤独感)
- 日本から取り残された感覚
- 海外駐在員に選ばれた自負
- 物理的・経済的な距離感
文化・価値観の違い
海外駐在をしてすぐに直面するのが、文化や価値観の違いです。これはありとあらゆる場面でついてきてしまう、悲しい現実です。最近は日本でも少しずつ価値観が多様化しつつありますが、元々日本という文化や価値観を共有できる人に囲まれている島国で生まれ育って来ていると、海外での文化や価値観の違いに戸惑うことが多いです。
イギリス、特に私の駐在しているロンドンの場合、移民の多い多民族な地域となっているため、その文化や価値観もまちまちです。ですが日本人にありがちな「人に迷惑をかけない」「他人に親切にするのは美徳」というような考え方はありません。
もちろん、会社の同僚や仲良くなった方であれば別ですし、すべてがそういった人ではないのですが、基本的には自分が嫌な思いをするのであれば、人に迷惑をかけても問題ない、親切にしてもらったらその人を使い倒す、という考え方の方の割合は日本よりもずっと多いと思います。
こうしたことを生活で感じるのは、例えばバスに乗るときの割り込み(そもそも列を作ることをしない)とか、車を運転していて危険な車線変更をしてくるとか、駐車場で決められた枠に駐車しないとか、共用で使用するものをきちんと返さないとか、アポイントの時間を守らないとか、例を挙げればいくらでも出てきます。
そういうものなんだ、と思うしかないのですが、頭でわかっていても心から理解することはできないです。日本人の方と話すと、海外生活ではこうしたことを「あきらめるしかない」とわかっているように言いますが、実際はそうした日本では当然のことを我慢しなければならない、見えないストレスが積み重なっているのだと思います。これは、自分のことを周りがわかってくれない孤独感に近いものがあると思います。
グローバルスタンダートの観点からは、問題があったら主張しなければならないのも事実で、日本人は総じて大人しいのだと思います。ですが、主張するのもクレームをつけるのも、元々そういうことに慣れていない日本人には疲れるのです。海外生活では我慢しても、文句を言ってもストレスが溜まってしまう、悲しい事実があります。
仕事の成果に対するプレッシャー
仕事の成果に対するプレッシャーが、日本国内で働いているよりも海外の方が強い、ということも考えられます。ここで、海外駐在員という立場は、どんなことが期待されるのでしょうか?
一般的には下記のようなことを期待されていると言われています。
- 定められたプロジェクトを遂行する役割
- 会社の有している技術を海外事業所に伝達する役割
- 日本と海外事業所の連携を円滑にするためのコミュニケーションの役割
- 特に定められたミッションはなく、役割も漠然としている
私が確認した中では、実は3番目の「日本と海外事業所の連携を円滑にするためのコミュニケーションの役割」と4番目の「特に定められたミッションはなく、役割も漠然としている」が多いです。言い換えれば、特に明確なミッションはなく海外赴任しているケースが比較的多いのです。
こうしたケースは、私としては海外駐在員にかかる負担が大きいと思っています。なぜなら、「特に明確な仕事は与えない、かつ特に何を期待するわけではないが、日本側が期待することは確実に実行しろ」という無茶振りをされているんです。
しかもこの点を、海外駐在員個人の素養やスキルに丸投げしています。実際のところ、海外駐在員が明らかな成果を挙げなくても問題ないのかも知れませんが、そんなことは当の海外駐在員は知るよしもありません。
そのため、「せっかく海外駐在させてもらったんだから、日本の期待に精一杯応えなきゃ!と」頑張ってしまう駐在員の方が多いのではないかと思います。
でも、これは割と絶望的なルートだと思います。基本的に海外駐在員は体力が通常の半分で戦っていると思ってください。いくら頑張っても成果を満足に挙げることができない可能性があります。もちろん例外もありますし、特に日本側から「このプロジェクトはなんとか成功に導いてほしい」といった明確な目標設定をされていれば別ですが、そうでない漠然とした役割の場合、成果を挙げることは難しいでしょう。
他責ということ自体いいことではなく、私は基本的には好きではありませんが、海外駐在に関しては、あまりにも駐在員の成果に関して外部要因が強く働いてしまうケースが多いと思います。「いくら頑張っても、無理!」そうした絶望感に苛まれる日本人駐在員は思ったよりも多いと感じています。


プライベートの問題(家族に関する問題/単身での孤独感)
続いては、プライベートの問題です。このプライベートの問題は海外駐在の方法により2つに分けられます。
家族に関する問題
1つ目は家族に関する問題です。家族帯同の場合、基本的には日本よりも危険な海外で、家族を守りながら仕事をしていかなければならないというのは、大きなストレス要因になります。
文化・価値観の違いの項目でも説明しましたが、日本とは異なる文化圏で様々な人種のいる中でのストレスは駐在員本人であっても耐え難いものがあります。家族帯同の場合は、家族も同様のストレスを抱えることになります。
例えば配偶者であれば、キャリアを中断して帯同しているような場合は、海外で専業主婦の立場になってしまいますので、生活の変化や社会的な孤立感に苦しんでしまうかも知れません。また、駐在員家族との付き合いや、子どもの友達家族との付き合いは、社会的なつながりが形成できるといういい面もあるかも知れませんが、付き合いが面倒だったり、我慢を強いられたりと悪い面もあるでしょう。
加えて、子どもがいる場合には海外での教育を受けることになりますので、現地校でのトラブルや日本の教育のキャッチアップ、日本語とローカル言語の言語の適応など、頭を悩ませるような問題が多く、大きなストレスになってしまうことが考えられます。
これらのストレス要因に対して、海外駐在員は家族からの要望に応えようと、必要以上の努力をしてしまう可能性があります。多くの問題は、簡単には解決できないのですが、何とか解決しようとして神経をすり減らしてしまい、自らの無力さを痛感する海外駐在員も多く見受けられます。
単身での孤独感
2つ目は単身での孤独感です。海外駐在が単身赴任のような、単身での駐在となる場合、家族帯同の場合とは異なり孤独感に苦しんでしまうことが考えられます。
海外駐在員として、仕事では日本人駐在員やローカル社員とのコミュニケーションをとることができますが、仕事以外の人間関係がうまく形成できていない場合、休日を一人で過ごすことが続いてしまい、孤独感や疎外感を感じてしま恐れがあります。
日本人コミュニティに参加するのもいい機会かもしれませんが、駐在先によっては日本人コミュニティがなく、現地のコミュニティに参加することとなり、コミュニティに溶け込もうとしても言葉の壁や文化の違いでうまく人間関係を築けない可能性があります。
日本から取り残された感覚
さらに、日本から取り残された感覚になってしまう、いわば断絶感もストレス要因として見逃せません。海外駐在中は、日本にいる友人や同僚とのつながりが薄れ、話題や価値観にズレを感じることが出てきます。いくらLineやFacebookなどのSNSでつながっていたとしても、物理的に会えるのと、ネット上でコミュニケーションしかできないのは雲泥の差があります。
ましてや会社の仕事という観点で見た場合、海外駐在員は日本では簡単にアクセスできていた情報にアクセスすることができず、日本から教えてもらうにも時差の関係でうまくコミュニケーションできず、情報が入手できなかったり、情報入手に多大な手間がかかったりと、苦労することが多いです。
こうした情報の不足は、自身で考えるよりも大きなストレス要因になる可能性がありますが、物理的な距離を縮めることは難しく、できるだけ日本の方とコミュニケーションして、情報を入手できるようにしておくしかありません。
また経済的に取り残される感覚も注意しなければなりません。日本側は海外駐在に起きている問題などにはほとんど気づいていないことが多いです。海外駐在員がイギリスのような物価の高い地域に赴任していると、貯金ができる余裕はなかなか見いだせません。日本であれば貯められるはずのお金を貯めることができず、「海外駐在員にならない方がよかったのでは?」と自責の念に駆られてしまう海外駐在員も少なくありません。


海外駐在員に選ばれた自負
もしかすると、海外駐在員の最も大きなストレス要因は海外駐在員に選ばれた自負、つまりプライドなのかも知れません。
一旦海外駐在員に選ばられると、その待遇の良さから、駐在員は「文句を言ってはいけない」「恵まれているのだから我慢すべき」という無言のプレッシャーがかかりやすく、それがメンタルヘルスの不調をさらに隠す原因にもなっています。
多くの海外駐在員は「今つらいけど、もしかして自分のせいでつらいのではないか?」と感じてしまい、会社や周りの方に自分に問題が起きているという悩みを口にできずに孤立してしまうのです。家族帯同であれば家族に相談できる可能性もありますが、その頼れるはずの家族が日常生活のストレスで参ってしまっていて、海外駐在員のケアまでできる状態にない場合も考えられます。
海外駐在のストレスは様々
ここまで説明した5つのストレス要因は、単独ではそれほど大きな問題に見えなくても、日々の積み重ね、およびいくつかが複合的に発生した場合には大きな負担担ってしまいます。そして、多くの場合、それが顕在化したときにはすでに心身ともに限界に達している、そんなケースも決して珍しくはありません。
このように、駐在生活には一見してわかりづらいが確実に存在するストレス要因が数多く存在します。多くの駐在員はそんな中でも何とか耐えていますが、私が聞いた限りでは、普通に過ごしていても、限界に近いところまで追い込まれている駐在員も少なくありません。
「そんなの日本にいても同じでしょ?単に甘えているだけじゃないの?」と思われるかも知れません。確かに他の多くの日本人駐在員は、メンタルの問題を起こさずに帰任を迎えるわけですから、問題に気づかなくても仕方がありません。ですが、海外駐在しているだけで体力が半分くらいで仕事をしている感覚になることは知っていただきたいと思います。
仕事もプライベートも、通常であれば耐えられるストレスも半分くらいしか耐えられない感覚です。場所にもよりますが、海外では「仕事のプレッシャー」+「海外の言語・文化・価値観の違い」+「日本からの疎外感」がそろってしまうと、自分ひとりで解決できない問題になってしまい、心が削られてしまいます。
よく見られるメンタルヘルスの問題とその兆候
 海外駐在生活におけるストレスは目に見えにくく、本人さえも気づかないうちに蓄積してしまいます。その結果として、心の不調やメンタルヘルスの問題が徐々に表面化していくことになります。
海外駐在生活におけるストレスは目に見えにくく、本人さえも気づかないうちに蓄積してしまいます。その結果として、心の不調やメンタルヘルスの問題が徐々に表面化していくことになります。
ここでは、海外駐在員に多く見られるメンタルヘルス上の課題と、その初期兆候について詳しく見ていきましょう。
うつ状態
まず、駐在員に多い心の不調として代表的なのが「うつ状態」です。これは決して“気分が落ち込む”程度のことではなく、やる気が出ない、何をしても楽しくない、集中力が続かない、理由もなく涙が出るなど、日常生活に大きな支障をきたす精神的な状態を指します。
最初は「ちょっと疲れているだけ」と自分に言い聞かせてしまう人が多いのですが、放置すると深刻化し、休職や帰国を余儀なくされるケースもあります。


不安障害
次に多いのが、「不安障害」です。新しい環境や仕事に適応しようとするあまり、「失敗してはいけない」「迷惑をかけたくない」というプレッシャーから、常に神経が張り詰めている状態になります。その結果、寝つきが悪くなったり、朝早くに目が覚めてしまったりするなど、睡眠障害を伴うことが少なくありません。
海外駐在で睡眠障害がある方は多いです。漠然とした不安感から夜早めに寝られずお酒を多く飲んでしまい、結果的に早く目覚めてしまう悪循環が見られるといった話をよく聞きます。
自己否定感・無力感
また、言語の壁や文化の違いからくる「自己否定感」や「無力感」も見逃せない問題です。日本ではできていたことがうまくできず、自信を失ってしまう。または「こんな簡単なことができないなんて」と自分を責めてしまい、自己評価が極端に低下することがあります。
先に体力が半分くらいでしか仕事ができない感覚について述べましたが、日本にいたときは普通にできたことが海外ではできないということは普通に起こります。言語の違いだけならまだしも、文化や価値観が異なり、環境も異なることからうまく行かないのは当然といえます。
孤立感
さらに、異文化環境での生活が長期にわたると、「孤立感」に苦しむ人もいます。現地のコミュニティにはなじめず、日本とも距離ができてしまい、自分の居場所がないと感じるようになってしまいます。これが進行すると、「誰にも必要とされていない」「存在意義が感じられない」といった思考に至り、より深刻なメンタル不調へとつながっていくことがあります。
Web会議やSNSのようなコミュニケーションツールは発展していますが、やはり実際に人に合うのと、ネット上のコミュニケーションでは大きな違いがあり、距離を感じてしまうことは海外駐在をしていると実感します。

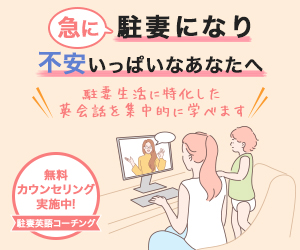
海外駐在のメンタルヘルスの初期兆候
これらの海外駐在におけるメンタルヘルスの問題には、共通して現れやすい「サイン」があります。以下のような兆候が現れた場合、無理をせず早めに休息をとったり、相談できる窓口に連絡することが重要です。
- 朝起きるのが極端につらい、または日中に強い眠気がある
- 仕事に集中できず、簡単な作業にも時間がかかる
- イライラしやすくなり、些細なことに過敏に反応してしまう
- 食欲が大きく減る、または逆に過食気味になる
- 休日なのに何もする気が起きず、ずっと横になってしまう
- 家族や友人との連絡を避けがちになる
- 「もうどうでもいい」「誰もわかってくれない」といった思考に支配される
これらは「ちょっと疲れているだけ」と見過ごされがちですが、心が出しているSOSのサインである可能性があります。特に海外駐在生活では、環境が大きく変わることもあり、「まだ慣れていないから体調がよくないだけで、自分は大丈夫」などと考えてしまい、こうした変化に自分で気づきにくくなる傾向があります。
また、身体面にも不調が現れることがあります。肩こり、頭痛、腹痛、動悸、過呼吸などの身体的な不調が続く場合、それが実はメンタルの問題に起因していることもあるのです。私が何人かの方から聞いたのは、意図せず涙が出てしまうというものがありました。これもメンタルがダメージを受けていることのサインを送っていたのかも知れません。

海外駐在でメンタル不調を感じたらどうする?
 海外駐在でメンタル不調を感じたときはどうすればいいでしょうか?
海外駐在でメンタル不調を感じたときはどうすればいいでしょうか?
メンタル不調を感じている中では難しいかも知れませんが、誰かに相談するというのが解決策として考えられます。問題の原因によって何が解決策になるかはわかりませんが、勇気を出して相談するというのが心の負担を少しでも減らすためには有効であると私は考えます。
上司や人事部門への相談
評価につながってしまうから怖い、と思われるかも知れませんが、自分の状況を周りの人に知ってもらうことは重要です。自分の直属の上司や、人事部門に自分の状況を知ってもらうことで、状況が改善することはよくあります。
人事評価でマイナスがつくと思って消極的になってしまうことはよくわかりますが、状況をより悪化させないためにも、勇気を出して声を上げるのは大事だと思います。上司や人事部門というのは、基本的にはこうした問題に対処する義務を負う存在であり、今の状況を変えてくれる可能性があります。
もちろん、その人がメンタル不調の原因になっている場合もありますので、その場合には別の対応を考える必要があるでしょう。
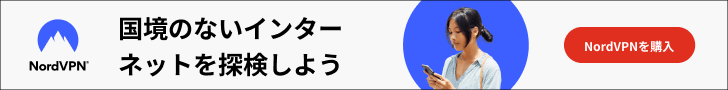
企業のサポート制度の利用
メンタルヘルスの問題を事前に察知するために、年に1回または2回の定期健康診断の中にメンタルヘルスチェックを含める企業が増えています。加えて、希望者にはカウンセラーとの面談ができる仕組みを設けているところもあります。
また、EAP(従業員支援プログラム)と呼ばれる、外部の専門機関と提携し、24時間電話やオンラインで心理相談ができるサービスを導入している企業もあります。駐在員だけでなく、帯同家族も利用可能としている例も増えています。
本社の人事部門が駐在員と定期的にリモート面談を実施し、業務状況や生活環境についてヒアリングを行うケースもあります。中には現地マネージャーを通じた間接的なフォローも含まれます。
GPや医療機関への相談
GPや医療機関への相談も重要な対応の一つです。GPへ行く場合は英語での対応となるため、言語面で難しい部分もあるかも知れませんが、真摯に対応してくれますし必要に応じて薬の処方などもしてくれます。
ロンドン医療センターのような、イギリスにある日本の医療機関であれば、相談は日本語で可能ですし、リモート診療の対応も可能ですので、困ったときには頼りになります。悩みを話すだけでも、気持ちが楽になることもありますので積極的に利用しましょう。

海外駐在員自身ができるセルフケアと予防策
 海外駐在員としての生活は、先に説明した通り仕事の責任や言語・文化の違い、孤独感など、さまざまなストレス要因が重なる環境です。こうした環境の中で、周りの支援だけでなく、自分自身で心身の健康を守るセルフケアの意識を持つことが非常に大切です。
海外駐在員としての生活は、先に説明した通り仕事の責任や言語・文化の違い、孤独感など、さまざまなストレス要因が重なる環境です。こうした環境の中で、周りの支援だけでなく、自分自身で心身の健康を守るセルフケアの意識を持つことが非常に大切です。
ここでは、海外駐在員自身ができるセルフケアと予防策について説明します。

ストレスの「見える化」と日々のセルフチェック
まず大切なのは、「自分の状態に気づく力」を高めることです。多くの海外駐在員は、「まだ大丈夫」と思いながら限界まで頑張ってしまう傾向があります。
1つの方法として、就寝前に「今日はどんな気分だったか?」「身体に違和感はないか?」など、自分に問いかけてみましょう。ここで重要なのはいつもと違っていないか、ということを確認することで、その違和感が継続しているかを自覚することです。
ライフスタイルを整える:食事・運動・睡眠
健康的な生活習慣はメンタルヘルスの基盤です。海外では日本とは違うリズムになりがちですが、基本を丁寧に整えることが、安定した気持ちを保つうえで非常に効果的です。
食事
「野菜・たんぱく質・炭水化物をバランスよく摂る」「外食やファストフードに偏らないよう、簡単な自炊の習慣を持つ」「地元の食材に親しむことで現地への抵抗感を減らす」といったことを意識します。病は気からという言葉にもあるように、食事は健康を保つためには重要な要素となります。
運動
「週に2〜3回の軽い運動(散歩・ヨガ・ジム・自転車)を取り入れる」ことに取り組みましょう。私はジョギングが趣味ですが、運動は海外駐在における仕事のストレス発散に大いに役立っています。日本人が参加するスポーツのコミュニティに参加するのも、話ができる仲間を作る上でも有効です。
睡眠
「就寝・起床時間をできるだけ一定にする」「寝る前のスマホ使用を控え、リラックスできるルーティンを作る(読書・瞑想・ストレッチなど)」を意識しましょう。夜お酒を飲む方は、あまり遅くに飲むのではなく、夕食時に量を控えめにすることで質の高い睡眠をとることが可能です。
孤立しないための人間関係づくり
海外では、人との関係が途切れやすく、孤独感が強まることがあります。しかし、たった1人でも「安心して話せる相手」がいることが大きな支えになります。現地の日本人会、趣味のサークル、SNSなどを通じて仲間を作ることが、海外駐在生活を支える糧になります。
日本人以外とのコミュニケーションでは、言語に不安があっても「挨拶」をして、少しずつ関係を築いていくことも重要です。駐在先には多様な人がいるとは思いますが、ある程度話をしていけば趣味や生活スタイルなど、自分に合う雑談できる人も見つかるはずです。
さらに、日本の友人や家族とも、定期的にオンラインで連絡を取り合うことも重要です。そうした方とは週に1回のビデオ通話など、都度連絡を取り合うことをおすすめします。
つらいときはとにかく相談する
「なんとなく元気が出ない」「朝起きるのがつらい」といった軽い不調のうちに、対処することが重要です。例えば思い切って1日有給を取ってリセットする機会を作ることや、頼れる人に相談することを心がけましょう。
些細なことであっても、誰かに相談できる環境があるだけでも相当救われる気持ちになって、改善が期待できるでしょう。これは友人や会社の人でなくても問題なく、医療機関やカウンセラーであっても大丈夫です。
とにかく「自分らしさ」を忘れない
海外という特殊な環境で「仕事だけの毎日」になってしまうと、心が摩耗していきます。「自分らしさ」を感じられる時間を少しでも持つことが、メンタルの安定につながります。
自分らしさを意識する方法としては、「写真、料理、語学学習、音楽など、自分が楽しめる趣味を見つける」「月に一度は自分をねぎらう日を設定し、好きなことをして過ごす」「日々の「小さな達成感」(掃除・料理・メール返信など)を意識して自分を認める」などで自己肯定感を高めていくことは、メンタルを保つために効果があります。
「無理しない自分」「逃げる自分」を許す
海外駐在員は、周囲からの期待が大きい分、「自分が頑張らなければ」というプレッシャーに常にさらされています。しかし、「頑張りすぎない」ことが非常に重要です。
特に、海外駐在員の仕事では「逃げることも選択肢の1つである」という点は意識しておきたいところです。「大事な仕事を前にして逃げるなんてとんでもない!」という意見が予想できますが、実際のところ逃げたところで問題はありません。それだけ大変なことをしているのですから。
それよりも、海外駐在員として日本から来ている自分が体調不良で帰国しなければならなくなることこそが、会社にとって大きな損失であることを意識しましょう。誰にでも不調な時期はありますし、海外であればなおさらです。
常に逃げ続けることは問題かも知れませんが、逃げ道の少ない海外での仕事の場合、逃げることを選択肢に入れておくかどうかは、心の余裕を持てるかどうかに影響します。そのため、受け入れがたいかも知れませんが、「逃げる」「無理しない」という選択肢を捨てないようにしてください。

まとめ
以上、海外駐在員のメンタルヘルスに関する心構えと対策について説明しました。ここでまとめておきます。
- 海外駐在員のメンタルは大変
海外駐在員メンタルの問題は他人にはわからないが、多くの人が問題を抱えている - 海外駐在員の抱えるストレスは膨大
生活のありとあらゆるところでギャップを感じ、あらゆるルールや物事を確認するにも文化や価値観が異なることから戸惑うことが多い - 海外駐在員の表からは見えないストレス
ー文化・価値観の違い
ー仕事の成果に対するプレッシャー
ープライベートの問題(家族に関する問題/単身での孤独感)
ー日本から取り残された感覚
ー海外駐在員に選ばれた自負 - よく見られるメンタルヘルスの問題とその兆候
ーうつ状態
ー不安障害
ー自己否定感・無力感
ー孤立感 - 海外駐在のメンタルヘルスの初期兆候
- 海外駐在でメンタル不調を感じたらどうする?
ー上司や人事部門への相談
ー企業のサポート制度の利用
ーGPや医療機関への相談 - 海外駐在員自身ができるセルフケアと予防策
ーストレスの「見える化」と日々のセルフチェック
ーライフスタイルを整える:食事・運動・睡眠
ー孤立しないための人間関係づくり
ーつらいときはとにかく相談する
ーとにかく「自分らしさ」を忘れない
ー「無理しない自分」「逃げる自分」を許す←重要!!
ありがとうございました。
<広告>
筆者のぷーたはイギリス駐在員を始めとする海外で生活する方にWiseのアカウントを作成することをおすすめしています。
Wiseのアカウント登録は、下にあるボタンから簡単にできます。日本にいる時からWiseアカウントは作成できますので、いざという時の安心のために、海外へ行く前に作っておくことをおすすめしますが、すでに海外に到着していても、住所が定まっていればイギリスをはじめ多くの国でアカウント登録が可能です。
こちらのボタンからWiseに登録すると、通常発行手数料が1,200円かかるWiseデビットカード、または最大75,000円までの送金に使えるクーポンのどちらかが無料でもらえます。
↓Wiseのアカウント登録(無料)はこちらから↓
Wiseの詳細情報、利用するメリット・デメリット、海外駐在員の利用するシーンなどはこちらの記事でくわしく解説していますので、よろしければご覧ください。